
※所属先については、令和7年6月末時点での情報です。
在学生インタビュー

中川 莉沙さん
HBMS 1年生(10期生)
マツダ株式会社
マツダ病院
臨床工学技士
臨床工学技士として10年、大学病院での高度急性期医療から慢性透析治療、医療機器管理を経験し、現在はマツダ病院で生命維持管理装置の操作や医療機器の管理など多岐にわたる業務に従事しています。
多職種で構成される病院組織において、臨床工学技士として病院経営や医療の質の向上、医療機器を介した医療安全を活性化させる組織マネジメント、直面している問題の課題解決力を養いたいと思っています。医療経営や人材マネジメントを学ぶには、医療の知見だけでは解決できない課題があり、時代の変化を恐れず、自分自身のアップデートをし続けるチャレンジャーでありたいと思い、HBMSに入学しました。
3年前から医療安全のプロジェクトとして、全国で発生している医療事故の情報収集や対応を検討していますが、現場では医療従事者の人材不足や業務効率化などの課題もあり、多様な職種が集まる医療現場で組織を動かすことは容男ではないと感じています。人を動かすために組織的な人材マネジメントの重要性を感じたことと、私自身も医療職としてこれからの時代を生き残っていくために、経営戦略、マーケティングの知識を身に付けたいと考えたことが、医療系大学院ではなくHBMSを選択した理由です。
現在はマーケティングや経営戦略などマネジメントの基礎知識の授業を受講しており、今まで知り得なかった知識を吸収できていると日々実感しています。
これまで医療業界一筋でしたので、経営の知識はほとんどありませんでしたが、10期生の仲間とともに切磋琢磨しながら、HBMSでの高度な学びに必死に食らい付いて、存分に知識を広げていきたいと思います。
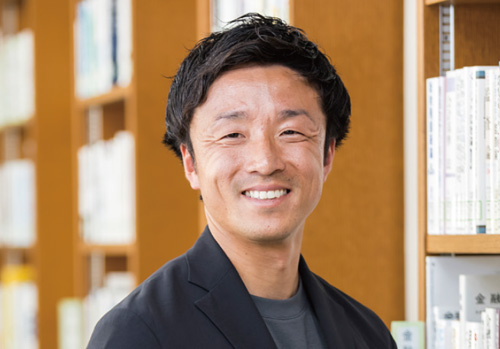
江藤 良輔さん
HBMS 2年生(9期生)
広川株式会社
経営企画部
課長
入学時と比べると、明らかに自分の視野が拡がリました。実践的なマーケティング、アカウンティング、ファイナンスなどを学べることは当然なのですが、授業でやらなければ全く関わらない領域や興味がない領域を考えざるを得ない状況があり、そんな環境に身を置くことで視野の拡がりを実感します。また、人との関係性が濃くなりました。同期生はみんな仕事や課題、目標が違います。そういう人たちとコミュニケーションを取ることで自分の視野が拡がりましたし、「この問題はあの人に聞こう」 「あの人に相談すれば誰か専門家を知っているかも」といった動きがとれるようになりました。HBMSがコミュニティ化されているので、人のつながリによってできることが増えましたね。
大変なことは、各クォーターの終わりにあるレポートや最終課題です。ただ咋年と比べると体としては慣れてくるもの。課題の1つや2つくらいでは焦らなくなりました。仕事とHBMSの両立は大変な時もありますが、どちらか一方を捨てるような考えはステージを1つ降りるということ。両方充実させてやりきるからこそステップアップだと思っています。
私は会社では新規事業の立ち上げと管理を担当しておリ、防災に関する事業を構築していますが、 HBMSの学びが実務に活かされていると感じています。たとえばマーケティング。売る仕組みや認知を拡げる仕組みをつくるにあたり、防災は社会的にはとっつきにくいイメージがあります。そういう中で、防災を事業として持続可能にしていくためには、どんな形に変えればいいのか、どの市場に持っていったらいいのかを考える上で、HBMSで培ったマーケティング能力が活かされています。
今、力を入れているのは「プロジェクト研究2」という卒論にあたるカリキュラムです。自分のテーマは「防災」で、まさに仕事と直結します。「地域に根差し地域に必要とされる企業であり続ける」という会社のビジョンと、広島に恩返ししたいという私自身のビジョンを実現するために、最後まで頑張りたいと思います。
修了生インタビュー
中年の転換期を学び直しにより軌道修正

石原 かおりさん
HBMS 3期生
株式会社Happy relations
代表取締役
一般社団法人ソーシャルケアビューティー
理事
2010年に美容室をメインとしたコンサルティングの会社を設立しました。起業してから勘と経験と体力任せで事業を進めていましたが、顧客に対して最先端のサービスを提供するには、自分自身がもっと学ぶ必要があると感じていました。HBMSで学んだことで、良かったことはたくさんありますが、人とのつながりを持てたことと、考え方を学び直せたことが特に大きかったと振り返ります。
経営に必要な知識を学べるだけでなく、自分で考え、実践して、検証することをできるだけ早く回すこと(PDS)を自然とできるようにもなったことは実務でも存分に活かせています。当時は漠然とわかったような気になっていたSDGsやコモンズなど物事の本質に触れ、わかるようになるまで学べたことも私にとって収穫だったと思います。
私の仕事の仕方は、入学前までは美容室の営業後の時間帯や土・日曜に及ぶこともあったため、初めは、仕事と学業の調整に苦労しましたが、これまでやっていた業務を人に任せるか、タイムアップするかの二択で整理しました。今では在学中に行っていた時間のやりくりを継続し、基本的に土・日曜は休みに。仕事のスタイルを見直すよいきっかけにもなったと思っています。
新たな視点を手に入れて理解の幅を広げる

小林 靖孟さん
HBMS 5期生
広島市立北部医療センター安佐市民病院
救急科 副部長
(広島大学 救急集中治療医学教室 所属)
日本救急医学会 救急科専門医
救急科の専門医として経験を積むなかで、指導的立場となりマネジメントや部門間連携の面で力不足を感じていました。私自身、専門技能を社会の価値に変換したいという思いがあったことから、医学博士や公衆衛生学、病院経営の修士ではなく、ビジネス的知見を広げるためMBAを目指しました。
知識やコミュニティを広げるため、アカウンティング、ファイナンスなど医療とは関わりのない科目を積極的に履修するよう心掛けました。その副次的な効果として、本来の専門である医学・自然科学の視点に加えて、経営・社会科学の視点を得ることができ、2つの視点で物事をより深く理解できるようになったと感じています。
ともに助け合い、悩み、刺激しあった同期の絆は固く、未だにみんなで集まってアイデア出しをしたり、ディスカッションをしたり、まるで学生の延長のようです。今は、同期が立ち上げた「ひろしまリビングラボ」など、まちづくりの活動にも参加しています。今後は救急医としての専門性も磨きつつ、医療や社会の課題解決に貢献できる人材になりたいと考えています。
突破のカギは方程式ではなくアスピレーション

松本 博治さん
HBMS 6期生
株式会社ダイセル
大竹工場生産部 セルロース室
担当リーダー
社内の長期ビジョン策定プロジェクトに参画した際、事業の変革や組織のイノベーションに関する知識がないことを痛感。知識だけでなく、実践を通して学んでみたいと考え、HBMSの門を叩きました。
入学当初は、成功や失敗といった多くの事例を学び、共通要素を理解すれば成功の黄金律が浮き彫りになると考えていました。しかし、2年間の結論は「そんなものはない!」ということ。成功企業の中には、従来の常識では非効率とも見える手段を選択し、イノベーションのジレンマを華麗に、泥臭く突破していました。成功の方程式はなく、さらに一見すると非効率なやり方であればあるほど、その一歩を踏み出すには勇気が必要です。この壁を超えるには、ベースとなる知識や理論はもちろんですが、強烈なアスピレーションが絶対条件です。業種も立場も年齢も違う同期とともに、それぞれが抱えるリアルすぎる課題、ジレンマ、そして夢を語り、共感しあうことで私の世界は一気に広がりました。世の中には無数の課題が存在していますが、その見え方、捉え方は2年前と大きく変わりました。人生に大きなインパクトを与えてくれるHBMSでの学びを通して、「誰かがやる。ではなく、自分たちがやる」というアスピレーションを持って、ともに新しい未来を描いてみませんか。
学びやスキル活かし 地域経済の循環を形に

登 景子さん
HBMS 4期生
株式会社ケン・リース
FROM EA TS PR 担当
HBMSのゼミ仲間が研究の一環として取り組むなかで発案して立ち上げた、FROM EATSという事業に修了後からチームメンバーとして参画しています。FROM EATSは、「食でまちを笑顔に!」をスローガンに掲げた、つくる人(生産者・飲食店)と、わたしたち食べる人(消費者)との繋がりをより豊かにすることを目指したプロジェクトです。地元野菜の定期便を軸にしたサービスと、農や食を楽しむコミュニティづくりに取り組んでいます。
ブランドをつくりあげていく段階なので、まさにマーケティングの授業で学んだことを実践しながら、改めて学び直しをしています。
在学中は、異業種の同期たちから多くの刺激を受け、講義やゼミでの学びを通じて、今いる場所で自分が目指したいものが明確になりました。「心が豊かになる地域経済の循環をつくりたい」という想いを共有する仲間に出会えて、FROM EATSの事業に参画できたのも全てHBMSがあったからこそ。授業時間以外にも家で取り組む時間も多かったので、サポートしてくれた家族にも感謝しています。
思考の広がりにつながる対面授業での学び

結城 奈津子さん
HBMS 8期生
マツダ株式会社 MDI&IT 本部
グローバル IT 業務部
アシスタントマネージャー
HBMSの魅力は、素晴らしい仲間との出会い、そして対面授業にあると感じています。画面から流れる映像や音声だけでは伝わらない「その場の空気感」も貴重な情報のひとつです。異なるバックグラウンドを持つ仲間の振る舞いや価値観に触れることで、自分の思考も大きく広がっていきました。私自身、入学当初は授業・仕事・家庭の両立に大変苦労しました。しかし、「ここで学ぶことは、自分だけでなく家族にとっても成長の機会になる」と考え方を切り替え、試行錯誤することで何とか乗り越えることができました。私は、家族と一緒にHBMSを卒業したのだと思っています。
これからHBMSに入学される皆さんに伝えたいのは、「一人で頑張ろうとしないでほしい」ということです。いろんな人の意見を間き、助けを借りてください。人を巻き込む力は、ビジネスでも大きな武器になります。今では、上司や同僚とのコミュニケーションの中で、情報を体系的に整理し、自分の考えを的確に伝えられるようになったという実感があリます。今後は、HBMSで学んだ実践的な知識やスキルを活かし、社内の課題解決のみならず、地域社会の課題解決にも貢献したいと考えています。
仲間とともに魅力的な地域を創造していきたい

國清 泰臣さん
HBMS 7期生
株式会社ホームテレビ
イノベーション事業局 地域共創事業部
プロジェクトリーダー
営業で3年、スポーツの現場で9年と、放送業界のど真ん中にいた自分が、新規事業担当部署への異動を機に、ビジネスやマーケティングを学ぶ必要性を感じてHBMSに入学。何が分からないのかが分からない状態から、課題に対して解決のヒントを手にするまでの時間を大幅に短縮できるまでに成長させていただきました。
卒業後、新規事業プロジェクトの一環として株式会社DoTSの立ち上げに携わり、広島駅ビル minamoa に広島・瀬戸内•世界の未来をつなぐ共創拠点「miobyDoTS」をオープン。今も日々多くの課題に直面しており、感覚的には3歩進んで8歩下がるというイメージですが、それが事業を創るということのリアリティですし、HBMSで自分の中に「基準」ができたからこそギャップに気付くことができている、と学びの成果を実感しています。
知識を得られたことはもちろんですが、それ以上にHBMSのつながりは何事にも代えがたいものです。先輩や同期の力を借り、遠慮なく相談ざせていただいたことが、事業創造の大きな必要要素となりました。信頼できる仲間と一緒に、これからも魅力的な地域を創っていきたいと思います。